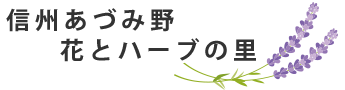池田町の祭り 【広津・陸郷地区】
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:563
池田町の祭り【広津・陸郷地区】
(1) 楡室(にれむろ)神社(実業)

牝の獅子舞 鼻が黒いのが特徴です

鳥居と社
祭り前の境内の掃除
【鎮座地】実業
【例大祭の時期】体育の日とその前日
【例大祭の内容】神事
日本総氏神であり、太陽を神格化した神様でもある天照大日霊命(あまてらすおおひるめのみこと)が祀られています。
慶安3年(1650)年の記録では「楡村」と残っており、これが変化して「楡室」となったと言われていますが、明確な資料は残っていません。
元々は例祭は2日間にわたり、近隣神社との結祭りとして神楽と獅子舞が2組奉納されていました。戦前は芝居や映画を鑑賞したり、戦後は青年団が素人演芸を披露したりととても賑やかでした。
戸数も減り今ではそれらは行われていませんが、祭りは地域の大切なものとして脈々と続いています。
(2) 津賀尾(つがのお)神社(栂ノ尾)

津賀尾神社の社

御嶽大権現碑
【鎮座地】栂ノ尾
【例大祭の時期】10月5日・6日
【例大祭の内容】神事
雷神・剣の神様である武甕槌命(たけみかづちのみこと)、諏訪社の神様である建御名方命(たけみなかたのみこと)が祀られています。神社の建てられた時期は記録が残っていません。かつては獅子神楽も行われていましたが、獅子頭が盗難にあい、現在は行われていません。また、別々だった秋葉社も一緒に祭りをするようになり、同じ日にそれぞれの神事を行います。
(3) 水堀神社(水堀)
水堀神社の社

祭りの準備はみんなで
【鎮座地】水堀
【例大祭の時期】10月1日・2日
【例大祭の内容】神事
室町時代の永享12年(1440)に建てられたと記録されています。
神社のある寺間、中ノ貝の地域をあわせて「水堀」と呼ぶことから、神社を水堀神社と呼ぶようになりました。
水の神様が祀られていて、かつては雨ごいの神事も行われていました。
(4) 松尾神社(北足沼)

厳かな神事

松尾神社の鳥居
【鎮座地】北足沼
【例大祭の時期】体育の日
【例大祭の内容】神事
元々の松尾神社は同じ北足沼の石造百体仏像がある場所に置かれていましたが、永和3年(1377)に大きな地すべりにあい、現在の場所に移されたと伝えられています。
地すべりがあったときに山城国の住人で源義治という人が来て御分霊を祀ったところ地鳴りが収まったことから、元々の産土神だった八幡宮に代わって松尾神社が産土神となりました。
(5) 八代神明宮(八代)

神事の前に社を清めます

八代神明宮の神主
【鎮座地】八代
【例大祭の時期】10月から11月の間の1日
【例大祭の内容】神事
日本人の総氏神である天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)が祀られています。
国宝にも指定されている大町市宮本の仁科神明宮(宮本神明宮)の分社として建てられました。
建物の造りは古い建築様式である神明造りで、仁科神明宮と同じ造りです。20年毎に神社の建て替えを行う式年遷宮でも仁科神明宮の残木を使って建て替えをするなど、仁科神明宮と関係の深い神社です。
また、その式年遷宮のたびに残されてきた棟札(むなふだ)は古いもので600年近い歴史があり、町の文化財にも指定されています。
(6) 樹玉(こだま)神社(有明)
祭りの準備ができた樹玉神社

女性神主が厳かに

1日目の夜の余興、三味線

新しい奉納太鼓・ジャンベ
【鎮座地】有明
【例大祭の時期】10月初旬の土曜日、日曜日
【例大祭の内容】神事、奉納太鼓
合併前の村である嶺方新田村の産土神(うぶすながみ)が祀られていて、神社が建てられた時の記録は残っていません。
明治5年(1782)から村の神社の一つとして認められるようになり、明治43年(1910)からは無格社諏訪社、大正9年(1920)からは伊勢宮無格社大明神、境内社鹿島社も一緒に祀られるようになりました。
木の神様である久々能智命(くくのちのみこと)や、諏訪社の神様でもある建御名方命(たてみなかたのみこと)、雷神・剣の神様である武甕槌命(たけみかづちのみこと)、日本人の総氏神であり日の神様でもある天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)の4つの神様が祀られています。
舞台が2台あったほか、地域の3つの若連がそれぞれに神楽や獅子舞を披露したり、歌舞伎や役者も来たりと、周辺の神社と比べてもとても賑やかな祭りでした。
現在は獅子頭は盗まれてしまい、神楽や獅子舞は行われていません。それでも提灯を新調し、太鼓(ジャンベ)の演奏を奉納したり、夜の余興として地域みんなでカラオケ大会をしたりと、新しい形で賑やかな祭りが今でも続けられています。
お問い合わせ
池田町(いけだまち)学校保育課 学校保育係(学校)
電話: 0261-61-1430
ファクス: 0261-61-1665
電話番号のかけ間違いにご注意ください!