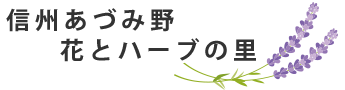国民健康保険
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:45
国民健康保険について
国民健康保険への加入の対象となる方
(1)池田町に住所がある方
(2)国民健康保険には、次の方を除くすべての方が加入しなければなりません。
- 職場の健康保険などに加入している方とその被扶養者
- 国民健康保険組合に加入している方とその世帯員
- 生活保護を受けている方
(3)外国人で、適法に3か月を超えて在留する方
届出(加入・脱退等)
国民健康保険に加入する方、脱退する方、その他変更のある方は、14日以内に届出てください。
| 手続きの種類 | こんなとき | 持参するもの |
|---|---|---|
| 国保に加入 | ほかの市区町村から転入してきたとき | 身分を証明するもの |
| ほかの健康保険をやめたとき | 健保などの資格喪失証明書、身分を証明するもの | |
| 子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、口座番号(世帯主)、身分を証明するもの | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、身分を証明するもの | |
| 外国籍のかた | 特別永住者証明書、または在留カード、身分を証明するもの | |
| 国保を脱退 | ほかの市区町村へ転出したとき | 資格確認書、身分を証明するもの |
| ほかの健康保険に入ったとき | 国保の資格確認書、健保などの資格確認書または健保などの資格取得証明書、身分を証明するもの | |
| 修学のため、池田町に住居がなくなるとき | 資格確認書、在学証明書、身分を証明するもの | |
| 生活保護を受けるとき | 資格確認書、保護開始決定通知書、身分を証明するもの | |
| 外国籍のかた | 資格確認書、特別永住者証明書、または在留カード、身分を証明するもの | |
| その他 | 資格確認書をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) | 身分を証明するもの(あれば使えなくなった資格確認書) |
| 住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 資格確認書、身分を証明するもの |
国保税の引き落としを希望される方は口座番号のわかるものと銀行印をお持ちください。
保険資格取得証明書または保険資格喪失証明書がない場合は申請書等から様式を印刷し、会社・事業所の担当の方に証明書の記入を依頼してください。
マイナンバーカードを保険証として利用できます
マイナンバーカードを保険証として利用するオンライン資格確認が、2021年10月20日から本格運用となっております。
マイナンバーカードを保険証として利用すると、窓口で限度額以上の支払いが不要になったり、マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできたりします。利用するためには、「マイナポータル」(別ウインドウで開く)で保険証として利用するための申込手続(初回登録)を事前に行う必要があります。(役場窓口や一部の医療機関等でも登録が可能です。)
国民健康保険の給付
保険医療機関で受診する際の一部負担金の割合は以下のとおりです。
なお、75歳以上の方および、65歳以上で障害認定を受けている方は後期高齢者医療制度(別ウインドウで開く)の給付の対象となります。
| 区分 | 負担割合 | 受診の際に医療機関に提出するもの |
|---|---|---|
| 0歳から小学校就学前 | 2割 | 資格確認書かマイナンバーカード(マイナ保険証) |
| 小学校就学後から70歳未満 | 3割 | 資格確認書かマイナンバーカード(マイナ保険証) |
| 70歳以上 | 2割 | 資格確認書かマイナンバーカード(マイナ保険証) |
| 70歳以上(一定以上所得者) | 3割 | 資格確認書かマイナンバーカード(マイナ保険証) |
入院時の食費、居住費について
入院時の食費
入院中の食事、居住費は、他の医療費とは別枠で自己負担となります。
| 区分 | 標準負担額 |
|---|---|
| 住民税課税世帯 | 一食510円 |
住民税非課税世帯または低所得者2(低所得者1を除く70歳以上の方で同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方)で過去12カ月の入院日数が90日以下 | 一食240円 |
| 住民税非課税世帯または低所得者2で過去12カ月の入院日数が91日以上。ただし過去12カ月の入院日数は、住民税非課税世帯または低所得者2として標準負担額減額認定証の発行がされている期間で計算します。 | 一食190円 (マイナ保険証を利用した場合でも申請が必要です) |
低所得者1(70歳以上の方で同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控え所額80万円として計算)を差し引いたとき0円になる方) | 一食110円 |
該当の方は、入院の際に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、申請してください。
マイナ保険証を利用している方は申請の必要はありません。
入院時の居住費
65歳以上の方が、療養病床に入院する場合は、介護保険で入院している方との負担の均衡をはかるため、介護保険と同様に食費、居住費を負担します。
| 区分 | 食費(1食) | 居住費(1日) |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 510円 (一部医療機関では 470円) | 370円 |
| 住民税非課税世帯(低所得者2) | 240円 | 370円 |
| 低所得者1 | 140円 | 370円 |
該当の方は、入院の際に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、交付を申請してください。
マイナ保険証を利用している方は申請の必要はありません。
その他受けられる給付について
| 番号 | 給付の種類 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 療養費 | やむを得ない理由で資格確認書を提出できなかったとき(海外旅行中を含む) |
| 2 | 移送費 | 移動困難であって、該当医療機関の設備では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院したとき。 |
| 3 | あんま、マッサージ、 はり、灸、接骨院等での施術費 | 保険医の同意があったとき ※ ただし、国民健康保険を取り扱う接骨院で施術を受ける場合は、通常、一部負担金の支払いですみますので、その際の手続きは不要です |
| 4 | コルセット等の補装具 | 保険医の同意があったとき |
| 5 | 出産育児一時金 | 被保険者が出産したとき 488,000円 (妊娠満85日以上の流産、死産であっても支給。また、産科医療保障制度に加入している分娩機関で出産した場合は12,000円が上乗せされ500,000円支給されます) |
| 6 | 葬祭費 | 被保険者の死亡について葬祭を行ったとき 50,000円 |
- 1から4について、あらかじめ住民課保険医療係にご相談ください。
- 5について、平成21年10月1日より医療機関への直接支払制度が始まりました。今までどおり出産育児一時金を受け取る方法もできますが、出産費用を払わずにすむ(出産費用が出産育児一時金の範囲内なら)直接支払制度をご利用ください。
- 6について、葬祭を行った方(喪主)が特定できるもの(会葬はがき、または領収書)、資格確認書、喪主の口座番号がわかるものをお持ちください。
医療費が高額になったとき
医療費の自己負担額が高額となったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満と70歳以上75歳未満では、自己負担限度額が異なります。
窓口での支払いが限度額までとなる場合
マイナ保険証を利用すれば、医療機関の窓口での支払いは限度額までになります。
マイナ保険証を利用しない場合は、外来、入院とも、一医療機関の窓口での支払いは限度額適用認定証(住民税非課税世帯、低所得者1、または2の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示することにより限度額までとなります。認定証の申請には住民課保険医療係へお越しください。ただし、保険料に滞納のある場合、認定証を交付できないことがあります。
申請により高額療養費が支給される場合
限度額適用認定証等を提示しない場合、複数の医療機関を受診した場合等で、医療費の限度額が超えた場合、申請して認められれば限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。
該当する方には高額療養費支給申請書をお送りします。申請書がお手元に届きましたら、住民課保険医療係で申請の手続きをしてください。なお、申請できる期間には時効がありますのでご注意ください。
70歳未満の入院に係る高額療養費
| 区分 | 所得区分 | 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降) |
|---|---|---|---|
| ア | 所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 所得600万円超から901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ | 所得210万円超から600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ | 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額が支給されます。
- 所得区分について、世帯の国保被保険者の基礎控除後の総所得金額の合計です。所得の申告がされていない場合(ア)とみなされますのでご注意ください。
- 同じ世帯内で合算して限度額を超えたとき は、同一世帯内で、同月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
- 自己負担額の計算方法
月ごとの診療について計算します 。
2つ以上の病院や診療所にかかった場合は別々に計算します 。
同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また、外来や入院も別々に計算します。
入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは支給対象外となります。
70歳以上75歳未満の入院にかかる高額療養費
外来の個人単位の限度額を適用後に外来と入院を合算した世帯単位の限度額を適用します。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
現役並み所得者3(同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がおり、かつ所得合計が690万円以上の方) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%。ただし過去12カ月以内に、外来+入院の限度額を越えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は140,100円になります。 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%。ただし過去12カ月以内に、外来+入院の限度額を越えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は140,100円になります。 |
現役並み所得者2(同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がおり、かつ所得合計が380万円以上の方) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%。ただし過去12カ月以内に、外来+入院の限度額を越えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は93,000円になります。 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%。ただし過去12カ月以内に、外来+入院の限度額を越えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は93,000円になります。 |
現役並み所得者1(同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がおり、かつ所得合計が145万円以上の方) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%。ただし過去12カ月以内に、外来+入院の限度額を越えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は44,400円になります。 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%。ただし過去12カ月以内に、外来+入院の限度額を越えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は44,400円になります。 |
一般(現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の方) | 18,000円 (年間の限度額は144,000円) | 57,600円。ただし過去12カ月以内に、外来+入院の限度額を越えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は44,400円になります。 |
低所得者2(低所得者1を除く同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方) | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1(同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたとき0円になる方) | 8,000円 | 15,000円 |
自己負担額の計算方法
- 月ごとの診療について計算します。
- 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算します。
- 病院・診療所、医科・歯科の区別なく計算します。
- 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは支給対象外です。
厚生労働大臣の指定する特定疾病
高額な治療を継続して行う血友病などや、人工透析が必要な慢性じん不全の方は、その治療にかかる一部負担金が1か月10,000円までになります。
ただし、70歳以上の方及び人工透析が必要な慢性じん不全の方で、現役並み所得者の方については、1月20,000円までになります。
該当する方は「特定疾病療養受療証」を交付しますので、医師の意見書、資格確認書を持って申請してださい。
高額医療と高額介護が合算される場合
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。 合算の期間は8月から翌年7月となります。
| 区分 | 所得区分 | 限度額 |
|---|---|---|
| ア | 所得901万円超 | 212万円 |
| イ | 所得600万円超から901万円以下 | 141万円 |
| ウ | 所得210万円超から600万円以下 | 67万円 |
| エ | 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 60万円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
| 所得区分 | 限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者3(課税所得690万円以上) | 212万円 |
| 現役並み所得者2(課税所得380万円以上) | 141万円 |
| 現役並み所得者1(課税所得145万円以上) | 67万円 |
| 一般(課税所得145万円未満等) | 5万円 |
| 低所得者2 | 31万円 |
| 低所得者1 | 19万円 |
申請書等
申請書など
 (高額療養費申請書のサンプル サイズ:173.91KB)
(高額療養費申請書のサンプル サイズ:173.91KB)申請書は世帯主に郵送されますので、そちらを使用してください。
 (限度額・標準負担額減額認定申請書 サイズ:246.27KB)
(限度額・標準負担額減額認定申請書 サイズ:246.27KB) 葬祭費申請書 (ワード形式、29.12KB)
葬祭費申請書 (ワード形式、29.12KB) 健康保険資格取得喪失証明書 (ワード形式、9.62KB)
健康保険資格取得喪失証明書 (ワード形式、9.62KB)
お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 保険医療係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!